記者M
新聞社勤務。南米と東南アジアに駐在歴13年余。年間100冊を目標に「精選読書」を実行中。座右の銘は「壮志凌雲」。目下の趣味は食べ歩きウオーキング。
軽井沢のホテルで総料理長を務める浜田統之さん(37)は今年、フランス・リヨンで開かれたフランス料理界で最も権威あるコンクール「ボキューズ・ドール国際料理コンクール」フランス本選に日本代表として出場し、24カ国のシェフたちと腕を競い、日本人として初めて3位に入賞した。
コンクールは、フランス料理界の巨匠ポール・ボキューズの呼びかけで始まったフランス料理の世界No.1シェフを決める大会で、フランス料理のワールドカップ(W杯)ともいわれる。
毎回与えられるテーマ食材(肉・魚)を5時間半で調理し、魚料理は皿盛りに、肉料理はプレートに12人分、皿に2人分それぞれ盛り付ける。味と盛付けのほかに、シェフの出身国のオリジナリティーが審査の対象になる。
大会の会場にあてられたリヨンのシラ国際外食産業見本市の多目的ホールは、文字通り「フレンチの鉄人」を決めるにふさわしい、びっくりするほど巨大なキッチンスタジアムである。
浜田さんは鳥取県境港市生まれ。特製の油揚げの中にお米と新鮮な野菜などを加え、じっくりと炊きあげた山陰独自の田舎料理「ののこめし」を製造販売する仕出し屋の次男として生まれた。
小さい頃から、母親が料理した販売用のきんぴらやおからなどの総菜を毎日食べさせられ、「甘い」だの「辛い」だのと感想を言ううちに、次第に確かな味覚が備わったのではないかという。
その浜田さんはいま、自らの仕事の拠点を、日本中(あるいは世界中)の食材が集まり、簡単に手に入れることができる東京ではなく、大都会から離れ、海がない長野に置いていることにこだわる。どんな食材でもすぐに手に入る東京なら、食材を選ぶのに苦労はしないが、それがために料理を創造する芽を自ら摘んでしまう恐れがあるからだという。ブタやコイなど長野特産の食材をどう調理し、最高の形で客にどう提供するか。野菜ひとつ取っても、農家の人たちと土壌づくりの段階から相談して育て、収穫するというこだわりようである。
「日本のフレンチで世界を魅了したい」。NHKラジオのインタビュー番組「日曜あさいちばん」に出演した浜田さんの控えめでありながら一本筋の通った語り口を聴きながら、「限られた世界でいかに独創性を発揮するか」という、分野や領域の枠を越えていつの時代にも共通する大きな命題について考え、ある一冊の本が頭に浮かんだ。
◆落ち込んで活字を追いたくないときに眺める
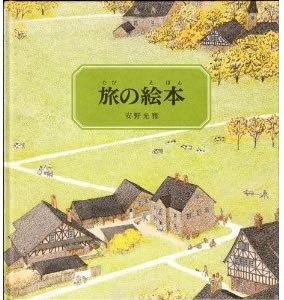 安野光雅の絵本『旅の絵本』(福音館書店、1977年)を初めて手にしたのは、新聞記者になりたての頃である。気分がすっかり落ち込み、目で活字を追うことなどとてもできない、そんな心境のときだった。
安野光雅の絵本『旅の絵本』(福音館書店、1977年)を初めて手にしたのは、新聞記者になりたての頃である。気分がすっかり落ち込み、目で活字を追うことなどとてもできない、そんな心境のときだった。
当時、社会部を志望していた僕は入社後、証券部に配属された。一番行きたくないと思っていたところだったので、がっかりした。僕以外の同僚はみな、ほぼ希望通りの部に配属されたらしく、その後「同期会」なるものがたびたび開かれたが、僕はいつも誘いを断った。おそらくは楽しいはずであろう仕事の話を聞くのが嫌で、嫉妬心に似たものがあったのかも知れない。
配属後、半年ほどして日本橋兜町にある東京証券取引所の記者クラブ「兜クラブ」詰めとなった。最初の仕事は、「場況」書き。取引所は当時、まだ機械化されておらず、各証券会社の「場立ち」と呼ばれる社員が、自分の担当するポスト(業種)の銘柄の売り買いを左右の手を巧みに動かして行っていた。売り買いとも早い者勝ちだから、場立ちのだれもが若くて、いかにも体育会系のような屈強な者が多かった。
売り買いが交錯する銘柄には場立ちが群がり、騒然となる。新人記者の場況取材は、その場立ちの城塞のような塊(かたまり)の中に入って、なんという銘柄が、どんな理由で売り買いされているのかを聞いて原稿にすることだ。
叩かれたり、こづかれたり、足を踏まれたりしながら、大混乱の中でなんとか場況1本分のネタを仕込んで記者室に戻り原稿用紙に向かおうとしたら、兜クラブ一筋ウン十年というベテラン記者が書いた場況が既にティッカーから流れているではないか。
彼らベテラン記者たちは場内には入らず、場内全体が見渡せる階上に設けられた臨時記者室の窓から、双眼鏡でのぞいている。場立ちが群がるポストがあればそれに照準を合わせ、彼らの手の動きだけで銘柄の名前と売り買いの株数がわかる。あとは、各証券会社との間に設けられた専用電話で場立ちの責任者に「なにがはやされてるの(なにが売り買いの理由なの)?」と聞くだけ。これで場況は一丁上がりである。
東証の取引時間は当時、前場(ぜんば)が午前9時から11時まで、後場(ごば)は午後1時から3時までと決められていた。新人記者の僕は取引が行われている間、場内と記者室の間を上ったり下りたりし、後場が終わると、証券会社の取材に駆り出された。
一番行きたくないところで、一番やりたくない仕事をさせられていると思っていた僕は時々、証券会社回りのついでに、書店で道草をした。この時に偶然出合ったのが、『旅の絵本』である。
絵本を開くと、最初、なにがなんだかわからなかった。文字はひとつもない。ページを繰っていきながら、ようやくこの絵本の狙いのようなものがわかってきた。これなら、現実から逃避できると思い、「きょうはこのまま引き揚げます」とキャップに電話を入れて自宅に直帰。絵本の中に出てくる旅人に自分を投影し、さまざま思い巡らせた。
それからしばらくして、ある証券会社のベテランアナリストに愚痴を聞いてもらっていたところ、「兜町の主(ぬし)のような記者と比べること自体おかしい」などと諭された。そして、「最近、青い眼が気になるんだよなあ」と、ヒントめいた言葉を口にした。
バブルが弾ける前の80年代初め、日本の株高をけん引した主役は国内の機関投資家だったが、徐々に「青い眼=外国人投資家」の日本買いが始まっていた。その実態はつかめなかったが、後場が終わり、翌日の前場が始まるまでの間にまとまった注文が入っていることがわかった。そこで僕は毎日早朝にクラブに出て、当時の4大証券(野村、日興、大和、山一)の担当者に電話を入れて外国人の投資動向を探り、それを記事にまとめて当日の前場が始まる前に流すようにした。
これはベテラン記者や証券会社の担当者にも好評だった。僕はようやく居場所を見つけたような気がした。ベテランならずとも新人には新人で、発想や切り口次第でまだまだ開拓できる領域がある、と実感できた。その後の記者生活で幾度となく同じような経験をし、そのたびにこう思い、自分を奮い立たせた。ないものねだりはしない、知恵を出せ、と。
◆中高年オヤジが絵本・・・・・・文句あっか?
『旅の絵本』はほかに、中部ヨーロッパ編、イタリア編、イギリス編、アメリカ編、スペイン編、デンマーク編、中国編、日本編と刊行されている。自分を絵本の中に登場する旅人に置き換えて、見開きのページをゆっくり眺めればいい。まもなく、ページ上にいる旅人(自分自身)が見つかるはずだ。
ここで、すぐに次に進まない。この旅の瞬間に、見開きの同じページの上でどんな場面(ストーリー)が展開されているかじっくり俯瞰するといい。そして、絵本をゆっくり眺める心の余裕を意識的に感じたい。中高年オヤジが絵本?なんてゆめゆめ思うことなかれ。
この夏の終わりに、東京都内のデパートで開かれていた「安野光雅が描いた御所の花展」に出かけた。安野が皇居・吹上御苑の四季折々の草花を描いた水彩画130点を展示したものだ。天皇皇后両陛下が住む御所がある吹上御苑には原生林に近い生態系が残されており、安野は2011年1月から12年4月にかけて約20回、一般の人が立ち入れない吹上御苑に宮内庁職員の案内で入り、スケッチを重ねたという。
僕のウオーキングコースの一つである皇居・東御苑でも見られるアヤメやロウバイが、それはそれは鮮やかな色で描かれていて、絵心のまったくない僕ですら画集がほしくなってしまった。絵をゆったり眺めるくらいの心の余裕を、いつも持っていたいものだと思う。











コメントを残す