記者M
新聞社勤務。南米と東南アジアに駐在歴13年余。年間100冊を目標に「精選読書」を実行中。座右の銘は「壮志凌雲」。目下の趣味は食べ歩きウオーキング。
関東地方はいま、晩秋から冬へとせわしく移ろうさなかにある。昼前はとくに空が碧(あお)く、空気が冷たくて心地いい。オフィスで机に座っているのが恨めしくなるほどだ。残念ながらオフィスから富士山は見えないが、荒川をわたって東京の対岸のすぐのところに住む僕の家からは、天気がよければ見ることができるし、通勤電車の車窓からもビル群の向こうに見える。この時期の富士山は空気が澄んでいて、どこから見てもとくにきれいだ。
南米での勤務を終えて1996年に帰国した後、99年にバンコクに赴任するまでの3年ほどの間、わが家では少なくとも月に1回は富士山に出かけた。春や秋は毎週のように出かけた。都内杉並区の社宅から中央高速道を経由して車で2時間ほど。富士山は、快適なドライブと雄大な自然を提供してくれた。
生前「音速の貴公子」と呼ばれたF1レーサー、アイルトン・セナの生まれ故郷ブラジルのサンパウロで僕はやっとこさ車に乗り始め、5年ほど住んでいる間にすっかり「スピード狂」になってしまっていた。帰国する前から日本に戻ったら乗る車を決めていた。今年免許を取った長男は、セナと同じ病院で生まれた。僕以上の「スピード狂」にならなければいいが……と気をもんでいる。
話がそれた。早朝の中央高速道を、富士山を目標にひたすら進む。富士山が少しずつ近づいてくる。はるか遠くに見えていた山頂が、いつのまにかフロントガラスに額をつけないと見えないくらい近くに迫ってくる。南米やメキシコではスピード違反で警察に何度も捕まり、そのたびにビール代をおごるなどして見逃してもらったが、日本ではそうはいかない。富士山に向けて何度か走っているうちに「ネズミ捕り」の場所がわかってきたこともあって毎回、ドライブを心ゆくまで楽しめた。
富士山の周辺は、訪れる人たちがみな「マイ富士」と呼ぶくらい、それぞれに人気のスポットがあり、広々とした空間がある。われわれはいつも車のトランクに子どもたちの遊び道具を積んで河口湖や山中湖の湖畔に車を止め、都内の社宅の小さな庭では到底味わえない開放感を満喫した。一時は山中湖の近くに住もうかと建て売りマンションに体験宿泊したり、町役場に年間の地震の回数や規模を問い合わせたりしたこともあった。
先週末、一泊二日で箱根を散策した。大涌谷や芦ノ湖の湖上から見る富士山もまた、格別だった。驚いたのは、箱根の観光地の行く先々で、にぎやかなタイのツアー客の一行と出くわしたことだ。今年、訪日ビザが免除されたことが最大の要因だとみられるが、ほとんどの人がタブレット端末を携行していた。日本人の若いカップルが「すげえ。タイ人のおばさんたち、みんなタブレット端末で写真を撮ってる!」と、知られざるタイのIT化にたまげていた。
話がまたそれた。その富士山が今年、ユネスコの世界文化遺産に登録された。富士山がさらに有名になるのはいいことだ。環境省関東地方環境事務所が四つある登山道の8合目付近に赤外線カウンターを設置して登山者数を調査した結果、今年は7月1日から8月31日までの登山者カウント数は計31万1千人だった。今年の富士山は9月2日に閉山したが、報道によれば、静岡県の初の調査では1万人以上が入山。山梨県側でも数万人が閉山後に登ったとみられる。
山頂まで文字通り数珠つなぎ状態になった「弾丸登山」の人たちを見ると、これからはのんびり富士山に登ることはできなくなるのだろうと、諦めにも似た気持ちになる。
◆日本の女性史、冒険史の一断面を活写
富士山は山頂に近づけば近づくほど命取りにもなりかねない危険な一面をはらんだ正体を現すようで、俯瞰(ふかん)するのがいいのかも知れない。12月1日のことだ。箱根ロープウェーで大涌谷から桃源台に向かっていた時、頂上付近をヘリコプターが飛んでいるのを見た。9・5合目近くで登頂を目指していた男女4人が滑落した事故の捜索活動だったことを、帰宅してから知った。
遠くから眺めると、雲ひとつなく澄み切った青空に、頂上から麓にかけて降り積もった雪の白さとのコントラストが絶妙で、巨大なパノラマを見ているような錯覚に陥っていた。しかしこのニュースを聞いて、そうやすやすと人を受け入れはしない富士山の冷徹さと自然の厳しさを改めて感じた。
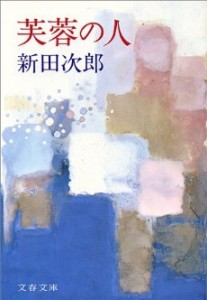 新田次郎の『芙蓉の人』(文芸春秋、1975年)は、1895年に富士山頂観測所建設の礎となった、野坂到・千代子夫妻による富土山頂での冬期気象観測の死闘を描いた作品である。
新田次郎の『芙蓉の人』(文芸春秋、1975年)は、1895年に富士山頂観測所建設の礎となった、野坂到・千代子夫妻による富土山頂での冬期気象観測の死闘を描いた作品である。
野中到は、世界でも例のない冬期高層気象観測を行うため、まだ厳冬期に頂上に立った人はいないという富士山頂での気象観測を行うという壮大な夢を抱く。妻の千代子は、夫の夢の実現がひとりでは無理なことを悟り、ひそかに夫を支えることを決意。今でこそ滑稽に思えるが、男尊女卑の風潮が強く、理不尽な男女差別が続いていた明治時代、女性はおろか男性でも山に登る人は極めてまれ、世間の目はもちろん、夫や姑などの批判や反対を押し切って富士山頂に向かう……。
著者の新田次郎はかつて富士山観測所に勤務し、通算400日以上富士山頂に滞在したことがある。山頂での観測生活がどれだけ過酷なものなのか、ノンフィクションさながらの細かな描写で一気に読ませる。
冬期富士登山が当時、どれほどの決死の冒険だったか。新田の別の著書『強力伝・孤島』(新潮社、1965年)に収められた『凍傷』の一節には「冬期富士山頂に登ったものは、それまで数える程しかいなかった。しかも明治二十八年(1895年)野中至(※原文のまま)夫妻の壮挙以来、十二年間は、一人として冬期富士山頂をきわめたものはいなかった。冬期の富士山頂登山は明らかに危険この上もない暴挙であると分かってからは、物好きで、登ろうとする者はいなかった。これは、野中夫妻の冬期富士山頂滞在の事実が大きな刺戟(しげき)を世人に与え過ぎたかも知れない」と指摘している。
新田はまた、『芙蓉の人』のあとがきの中で、この作品を書くことになった経緯を「現在の世に、野中千代子ほどの情熱と気概と勇気と忍耐を持った女性が果たしているであろうか。私は野中千代子を書いていながら明治の女に郷愁を覚え、明治の女をここに再現すべく懸命に書いた」と説明している。そう、日本の女性はいまでこそ、世界を舞台にさまざまな分野で活躍しているが、その先駆的な役割を果たした野中千代子を活写することは、日本の女性史、冒険史の一断面を紹介することでもあったのだ。
「芙蓉」とは、富士山の雅称である。文字通り、優雅な響きがあるが、この作品には、タイトルとは裏腹の無慈悲なまでの苛酷(かこく)な自然に立ち向かった命懸けの人間の生きざまが強く、深く刻み込まれている。











コメントを残す