記者M
新聞社勤務。南米と東南アジアに駐在歴13年余。年間120冊を目標に「精選読書」を実行中。座右の銘は「壮志凌雲」。目下の趣味は食べ歩きウオーキング。
「滝のトイレは向かって右側にあります」
もうずっと前のことだが、8年ぶりに帰国してJRの最寄りの駅で降りてトイレに行こうとしたら、自動音声でこんなやさしい女性の声のアナウンスが流れてきた。
「しばらくいない間に日本もまた随分進んだものだな」と感心した。トイレの中に日本庭園をしつらえ、そこに小さな滝を造っているのだ。その滝の流れの音に小便や大便の音が包み込まれるようにして同化していく……。これなら、だれも安心してゆっくりと用が足せる。日本人の奥ゆかしさをハイテクで具体化した一例である。
そんな馬鹿な。そんなこと、あるはずがない。その後、何度かこのトイレの前を通ってアナウンスを聞いているうちに、「滝のトイレ」は「多機能トイレ」であることに気づき、隣の男性用トイレで用を足しながら、一人で笑ってしまった。お年寄りや体の不自由な人たちのためにさまざまな機能が備えられたトイレのことで、以来、ほとんどの駅や公共施設に設置されていることがわかった。
いまも、このトイレの前を通るたびにこのアナウンスを耳にして、「これは、『滝のトイレ』ではなくて、『多機能トイレ』のことを言ってるんですよ」と、見ず知らずの近くの人に説明したくなる。
週刊朝日で連載中の『弘兼憲史のパパは牛乳屋』を初めて読んだ時の「感動」も同じようなものだった。「『パプアニューギニア』と『パパは牛乳屋』、意味はまったく違うけど、似ています。正しくは、音韻連想。馬鹿にした言い方では、オヤジギャクとなります。若い奴等(やつら)に負けてはいけません。このコーナーでネタを仕込み、今宵(こよい)も酒場で連発してウサを晴らしましょう。」というのが、毎回のうたい文句である。
社長を退任し現在会長の「島耕作」の課長当時の姿を描いた漫画「課長島耕作」のシリーズは、サラリーマンならだれでも一度は読んだことがあるはずだ。一方、時にはシニカルだったり下ネタがあったりするこの「パパは牛乳屋」を読むと、世の中にはさまざまな音韻連想があるものだと感心させられる。
まだ、高校の頃だったか。腹をすかして学校から戻り、家に入るなり母に「なんか(食べる物は)ない?」と尋ねたところ、「大都会パートⅡ」と母が答えた。俳優石原裕次郎が率いる「石原軍団」の刑事ドラマの再放送が当時放映されていたのだが、受験を控えてイライラしている上に腹がすいていたこともあって、僕は「テレビのことなんか聞いてへん!」と大声で怒った。すると母は「台所にパンがある、ってゆうてるやないの! 聞こえへんかったの?」と怒り返してきた。
この音韻連想の思い出はその後もずっと覚えていて、家族で話題にするたびに大笑いとなるが、今年84歳になる母は「そんなことゆうたかいな?」とすっかり忘れてしまっている。
音韻連想でいえば、ラオス生まれの妻の誤解を例示すれば、ちょっとした冊子になりそうなくらいだが、家族でゲラゲラ笑ったきり、その場でメモをしておかないのですぐに思い出せない。どれも、その場では笑い話ですませられるが、まったく知らない言語の習得には継続的な努力と言語に対するどん欲なまでの好奇心が欠かせないことを改めて実感する。
◆櫂や舵のない船で大海に乗り出す先駆者
この春、大学2年の長男が交換留学生としてタイで生活を始めた。幼稚園から中学2年まで過ごした第二の故郷で、本格的にタイ語を学ぶためである。
留学が決まった後、僕はタイ語を専門とする友人・知人にお薦めのタイ語の辞書について尋ねてみたが、全員が『タイ日辞典』(富田竹二郎著、養徳社刊)と口をそろえた。
日本で初めての本格的なタイ語辞典とされる2分冊の大著は、1987年の発刊当初は3万円で売られていたが、改訂第3版で絶版となった。息子はすぐに版元に電話をしてみたが、在庫はなく再版の予定もないとのことだった。
東京・神田神保町でアジアの本を専門に扱う内山書店(旧アジア文庫)や日本タイ協会でも親切に探してくれたが、残念ながら古本としても在庫は見つからなかった。幸い、アマゾンで新品同様のものが1冊だけ残っていて、約4万円の値段だったが、長男は祖母からもらった祝い金で思い切って購入した。
僕もネットで色々調べてみたが、やはりこの辞典は市場には現在ほとんど出回っておらず、プレミアが付いて最高で10万円近い値段になっていることがわかった。この辞典を薦めてくれたタイ語の専門家の一人は「そんなに高値が付くってわかっていたら余分に買っておけばよかった」と冗談半分で話した。
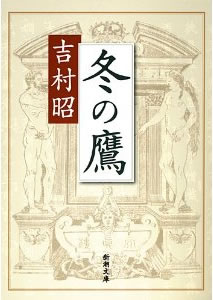
息子がタイに出発する前日の夜、僕はトランクに荷物を詰めていた息子に、餞別代わりに吉村昭の『冬の鷹』(1976年、新潮文庫)を手渡した。折しも東京・上野の国立科学博物館で6月半ばまで特別展「医は仁術」が開かれているが、その目玉となる展示品の一つでドイツの医学書のオランダ語版『ターヘル・アナトミア』を初めて日本語に翻訳した『解体新書』が誕生するまでの曲折と、翻訳に関わった人たちのその後を描いた写実的な物語である。
『解体新書』の著者は一般に、杉田玄白とされている。高校日本史でそう習った覚えがあるが、実際は蘭学者の前野良沢がほぼすべての翻訳を担当した。
良沢は長崎留学中に『ターヘル・アナトミア』を入手。それをなんとか日本語に翻訳しようと話を持ちかけた相手が玄白らであった。長崎のオランダ語通詞(通訳)らの助言も受けて実際に玄白の手で発行されたのは、良沢を中心に翻訳を始めて3年5カ月後のことだが、蘭学者の良沢でさえ言語としてのオランダ語にはあまり通じていなかったほか、玄白にいたってはオランダ語がまったく理解できなかった。
この2人に中川淳庵や桂川甫周らが加わって翻訳作業を始めるのだが、良沢以外はまるでちんぷんかんぷん。時に真剣に、音韻の連想で単語の意味を探ったりした。大の大人が一つの部屋にそろいながら、『ターヘル・アナトミア』の中の単語のわずか一語も訳出できないまま一日が終わってしまうこともあった。玄白は晩年に、著書『蘭学事始』の中で苦難の連続だった翻訳作業について「櫂(かい)や舵の無い船で大海に乗り出したよう」と表現した。
だから、たった一つの単語が理解できた時の「やりましたぞ! わかりましたぞ!」という弾(はじ)けるような喜びようは、読んでいてもわが心が躍るようでほほ笑ましく、彼ら日本医学の先駆者の執念に頭が下がる思いである。
良沢が『解体新書』の著書に自らの名前を連ねることを拒んだ理由も、究極を求めようとする学者としての矜持(きょうじ)の表れだった。辞書もない中で、まるで暗号を解読するような骨の折れる難作業。翻訳が完了したからといって、それが適訳かどうか確認できる術(すべ)もなく、良沢は翻訳の不備を自覚し、それを恥と感じ、著者として自分の名を世に出すことを拒んだとされる。
辞書の編纂(へんさん)作業には、だれにも負けないくらいの言葉への強い執着心と粘り強さが求められる。2012年に本屋大賞を受賞した三浦しをんの小説『舟を編む』(2011年、光文社)の中に出てくる主人公もその一例だ。
日本とタイの関係がこれだけ緊密になり、タイ語の需要がいっそう高まるなかで、いまだに富田の『タイ日辞典』を超える内容のタイ語辞書が出てこないのも、少し寂しい気がする。息子が『タイ日辞典』をページがすり減るほど使い込み、その合間に『冬の鷹』を読みながら将来を見すえ、一つ一つの言葉にいっそう強い執着心を持ってほしいと願っている。











コメントを残す