山口行治(やまぐち・ゆきはる)
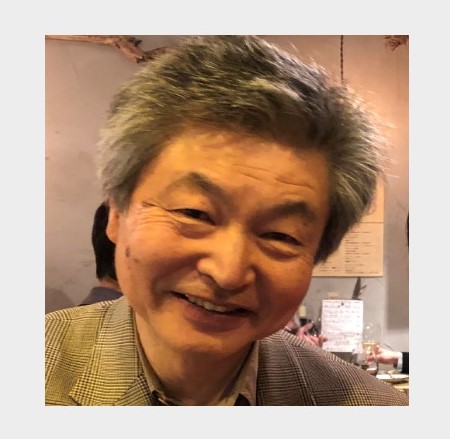
株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。
週末農夫は農閑期となり、読書量が増えてきた。新型コロナウイルスの緊急事態宣言で、県をまたぐ移動が制限されたとき、週末農夫としての生き方に本腰を入れるため、栃木県に住民票を移した。東京への出稼ぎ生活ではあるけれども、幸いデータ解析はリモートワークが主体なので、種まきのような待ったなしの作業ではない。週末農夫は、行政的には二地域居住者と表現されるようだけれども、このようなマイノリティーへの行政サービスは整備されていない。二地域居住者を意識した情報サービスが、地方生活者および地域産業への情報サービスとしても未来志向に「共助」できるように、NPO活動を始めた。農閑期こそ、新しいチャレンジの時期でもある。
前回第6回の「ゼロ神論」では、17世紀スピノザ哲学について考えてみた。SNS(ソーシャルネットワークシステム)やAI(人工知能)の倫理的な意味での剰余所与論を模索するためだ。余談になるけれども、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の政治的な意味での剰余所与論のほうが「屋台村的ニュース性」があるので、「ゼロ神論」については手短に展望をまとめることにする。剰余所与論として考えるのは、SNSによる社会的分断やAIによる社会的差別といった、大きな倫理ではなく、技術的な課題に隠された、無反省かつ無自覚に進行している小さな倫理の問題だ。小さな倫理の問題ではあっても、哲学的にはスピノザ以降の天才たちと対峙することになる。デイビット・ヒューム(18世紀の英国哲学者)とウィトゲンシュタイン(20世紀の英国で活躍した哲学者)の哲学を振り返って、論理的な因果関係の、哲学的な限界を明らかにしたい。科学の立場からの自然は論理ではなく数理で表現されるため、特にコンピューターにとっての自然は「データ」であるため、言語論的な倫理観ではSNSやAIの小さな倫理の問題をとらえきれない。本稿のタイトルである「数理哲学期待論」としては、因果関係に依存しない、数理的な倫理観としての「多様性」について考える。
そもそも、プラトンがソクラテスの全てを語りつくす自己言及的論理と、ピタゴラス学派の数が世界を支配するという密教的数理を融合して、合理的で開かれた高等教育を目指したことが「哲学」の始まりだった。プラトンの奇想天外な発想は、哲学の自由の源泉であって、哲学に不可能はない。デカルト・スピノザ・ライプニッツに始まる近代哲学は、哲学の自由を全ての自由へと拡大解釈した。その拡大解釈に条件を付けたのがデイビット・ヒュームの因果論的な経験論(本当はヒューム独特の自然主義)だった。哲学の自由とはいっても、実験的検証に耐える(思考実験も含めて)学問であるためには、哲学をする人間自体の本性による制約を受け入れなければならない。自然現象を原因と結果の論理的関係として理解するのなら、ヒュームの議論は的を得ている。ニュートン力学や相対性理論の範囲までであれば、少なくとも大きな矛盾はないだろう。しかし、量子力学や複雑系の科学まで範囲を広げれば、自然現象は人間の論理を超えていることは明らかで、確率的現象または偶然性を、人間の理解の限界としてではなく、自然の本質として認めざるを得ない。
哲学の自由に対するヒュームの制約は「最小限」のもので、カントやウィトゲンシュタインよりも控え目だった。ウィトゲンシュタインになると、哲学から自然を排除して、哲学を論理の枠組みで「最大限」に制約してしまう。数学を論理で制約する(基礎づける)試みは、数学的にも(ヒルベルトの公理論的立場)、論理学的にも(ラッセル・ホワイトヘッドのプリンキピア・マテマティカ)当初の目論見(もくろみ)のようには容易ではない。論理を人工言語(記号と記号の操作)と考えると、プログラミングはまさに人工言語そのものだけれども、プログラミングには「データ」という自然が介在するので、論理的制約からの自由がある。筆者のような「数は実在する」という強い実在論の立場からは、現在の人間が単純に理解しうる論理(古典論理)は弱すぎる。より強い公理や推論規則を追加することは可能だけれども、どの程度強くすることが妥当なのか、だれも答えることはできない。京都大学の望月新一教授がABC予想を証明したように、より強い数学(可能なすべての数学体系)で証明したとしても、私たちが理解しうるそのうちの一つの数学がどのような数学なのかは教えてくれない。しかし、数学の自由に哲学の自由も見習ってほしいものだ。
筆者の主張を単純化しよう。近代哲学の自由を、ヒューム以降の哲学は論理によって制約してきた。同時に、哲学は数学を見失っている。現代の過剰に人間中心な世界にとっては、哲学の自由が制約されることも、場合によっては脱構築されることが望ましいことにも異論はない。しかし、過剰に人間中心な世界となったのは、哲学が数学を見失ったことが原因だとしたらどうだろうか。過剰に人間的だから、「原因」もしくは犯人を捜したくなる。物質の実在性を信じるのと同程度に数の実在性を信じることができれば、光量子の実在性と同程度に虚数の実在性を信じることになる。たとえ光量子も虚数もよく理解できなかったとしても、その実在性を信じる立場だ。そして筆者は、最も強い仮定として、真の乱数(コンピューターが作成する疑似乱数ではなく)の実在性も信じる。
哲学における数理の不在が、倫理における数理の不在となり、小さな倫理を見失わせているというテーゼが、剰余所与論にとっての数理哲学期待論となる。デカルトは座標を発明し、ライプニッツは微積分学と二進法を創出した第一級の数学者だった。スピノザは幾何学的秩序に従って倫理書「エチカ」を構想した。現代のエチカは統計的分布に注目する。本稿で十分に議論することはできないけれども、グローバル化した資本主義社会において、経済的格差が社会の許容限界を超えているとすれば、それは社会の多様性が失われていることを意味するのではないだろうか。分子気体運動論においては、個体差のない分子の運動によって、エネルギーの分配は最大の格差(指数分布)を生じさせる。人間的な直観に反する結果だけれども、SNSやAIなどの技術が社会の多様性を阻害する方向に作用するかどうかは、賃金や犯罪などの社会的指標の分布をみればわかるという議論は検証可能だ。高等教育が社会の格差を拡大するという議論も、現代の高等教育が多様性や個体差をどの程度受け入れているのかを考えると分かりやすい。政治的な民主主義の議論が、数学を見失った哲学によって無批判に受け入れられているとしたら、哲学ができることは哲学の批判だけではなく、ライプニッツ以降の数学を勉強し直すことではないだろうか。AI技術者の機械学習とは別次元の、哲学的機械学習に結実することを期待している。
--------------------------------------
『剰余所与論』は意味不明な文章を、「剰余意味」として受け入れることから始めたい。言語の限界としての意味を、データ(所与)の新たなイメージによって乗り越えようとする哲学的な散文です。カール・マルクスが発見した「商品としての労働力」が「剰余価値」を産出する資本主義経済は老化している。老人には耐えがたい荒々しい気候変動の中に、文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試みです。











コメントを残す