山口行治(やまぐち・ゆきはる)
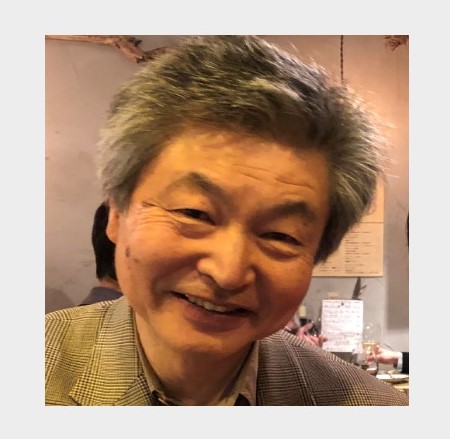 株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。
株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。
今年は雪が深い。農園には雪の下の白菜やネギなどがあり、野菜は甘くなっているけれども、収穫は困難だ。春の雪どけを待つしかない。農作業を同じ場所で15年以上継続していて、同じ天候はない。ソビエト型の計画経済が失敗したのも当然だろう。それでも素人の多品種少量栽培は、完全無農薬有機栽培で美味(おい)しいと、しだいに人気が出てきている。カエルや蝶だけではなく、サルにも人気があるので困ったものではある。
雪どけを待つ軽トラ=2021年12月29日 筆者撮影
『ウォールデン森の生活』(ヘンリー・D. ソロー、小学館文庫、2016年)は古典文学として高尚(こうしょう)すぎるので、あこがれの対象ではあっても、何度読んでも身につかない。一方で、『スモール・イズ・ビューティフル』(F・エルンスト・シューマッハー、講談社学術文庫、1986年)は読みやすく、続編や著者自身の解説もある。どちらも産業革命以降の近代文明からのオルタナティブ(別の道)を模索している。機械が製造した工業製品に囲まれて生活していると、自然との関係が間接的なものとなり、長期的な視野での思想的な方向性を見失いやすくなるという問題意識も似ている。前稿(『週末農夫の剰余所与論』第22回、砂漠緑化の地球内科)では、哲学としての技術論について考えてみた。産業革命は熱力学を生産や輸送の技術に応用することから始まっている。その後も、電磁気学が通信技術に応用され、相対性理論が原子爆弾を生みだし、現在は量子力学が産業応用されつつある。産業革命以降は、科学技術(Science & Technology)の時代といっても言い過ぎではないだろう。科学(Sciences)や技術(Technologies)は複数形で語られることが多いのに、科学技術(Science & Technology)には複数形がふさわしくないようだ。おそらく、科学技術を国家戦略とする覇権国家の単数性が影響しているのだろう。
エルンスト・シューマッハーは先進国の高度な技術ではなく、多くの発展途上国で、すぐに活用できる「中間技術」を提唱した。インドの巨人、ガンジーも手紡(つむ)ぎを新産業として推進することを提案したけれども、政治的に失敗している。技術には社会主義的な発想、もしくは計画経済はなじまないのだろう。それでは、技術が誕生する以前にさかのぼって、科学技術が見落とした「技術」(Technologies)を再考してはどうだろうか。工芸(アート)の世界だ。最先端の人工知能(AI)技術もアートの世界(例えばGAN〈Generative Adversarial Networks〉:敵対的生成ネットワーク)に近づいている。AI技術というと、グーグルなどの巨大企業が独占しているかのように思われるかもしれないけれども、実際は多数の無名なインドのプログラマーが推進役なのだ。筆者の経験からも、プログラミングは代表的な「中間技術」であって、決して少数の覇権国家や巨大企業が独占できるような技術ではない。データサイエンスが通常の意味での「科学」ではないことを認めてもらえれば、プログラミングが科学技術でないことも明らかだ。プログラミングは数学よりも工芸としての「アート」に近い。
科学技術&アート(Sciences Technologies & Arts)は3次元の複数形で、単純な幾何学では想像できない多様性がある。ユークリッド幾何学のような、単純な論理と線形性の世界では、3次元と4次元のもつれの世界は理解できない。科学技術&アートはプログラミングだけではない。完全無農薬有機栽培も仲間に入れてもらいたい。美味(おい)しい調理法まで含めれば、科学技術&アートとなる。筆者は、スコットランドの寒村における古代リーク(下仁田ネギのようなもの)のスープを、科学技術&アートとして鮮明に記憶している。中世のリークの種を栽培して、中世の食事を再現したものだ。ジャガイモやタマネギが導入される以前のスコットランドの食事だ。人類の味覚は大きくは変化していない。中世で美味(おい)しかったものは、現代でも美味(おい)しい。タンパク質としての貝食も筆者には懐かしい味だった。
科学技術&アートの幾何学に言及したのは、筆者のスピノザ理解の深化を書き留めたかったからでもある。17世紀オランダの哲学者、バールーフ・デ・スピノザの主著『エティカ‐幾何学的秩序によって証明された』はユークリッド幾何学の形式で論考されている。そして、当時流行し始めていたニュートン力学的な決定論を徹底している。しかし、スピノザ自身は幾何光学を得意とするレンズ磨き職人であったこと、何よりもスピノザの「自由」が17世紀とは思えない、とても現代的な視点であることから、この哲学書は難解なだけではなく、謎が多く違和感をともなう。筆者は、筆者自身を含めて、もしかしたら著者であっても、誰も『エティカ』の本当の意味を理解できていないのだと思う。そこで、スピノザの幾何学は、過去のユークリッド幾何学ではなく、未来の位相幾何学であったと仮定してみよう。位相幾何学は、幾何学的な変換によって変化しない図形や空間の普遍的な性質(不変量)を見いだし、その性質を数学的に厳密に研究する。例えば、ニュートン力学の微分方程式の解を求める問題の場合に、方程式の解が変化しない幾何学的変換を研究して、方程式の解が存在する条件を明らかにする。無限次元の関数空間の幾何学だ。無限次元の幾何学では、3次元や4次元の幾何学のようなもつれが発生しないために、実際は取り扱いやすいのだけれども、深入りはしないようにしよう。現代のスピノザ主義者として有名なアインシュタインの幾何学は、もちろん位相幾何学だ。スピノザの時代には存在しなかった位相幾何学の不変量を、生き方の不変量として、スピノザは「神すなわち自然」の中に感じていたのではないだろうか。
何の根拠もない勝手なスピノザ解釈を続けよう。スピノザの「力」の概念も独特で、「力能」と訳されたりする。この力能は、ニュートン力学の「力」ではなく、未来の熱力学の「自由エネルギー」のほうが近いような気がする。ニュートン力学は微分形式の力学だけれども、スピノザの力学は熱力学、電磁気学や量子力学のように、未来の積分形式の力学なのかもしれない。そう仮定すると、「力能」が最大に発揮される状態を「自由」という気持ちが理解できる。さすがのスピノザであっても、統計力学や量子力学における「確率」の問題までは見通せていなかったようだ。スピノザの神は、サイコロ遊びをしないのだ。
科学技術&アートの話が、なぜかスピノザの話になってしまった。途中、長い論理的な飛躍があって、科学技術&アートは個人の活動か組織の活動かという問いに答えようとしている。アートは個人の活動で、科学技術は組織の活動であることはだいたいわかる。より正確には、科学技術&アートの場合、普通の意味での組織における企業倫理とは次元の異なる、より本質的な意味での組織の倫理「エティカ」が問われるのではないかと考えている。企業倫理は「価値」、特に社会的なもしくは経済的な価値を問題としている。しかし「価値」は「意味」が明確なものにしか定義できない。だからスピノザは定義にこだわっているのだと思う。宗教的な倫理や生命倫理などでは、意味不明な論述や、多くの場合に意味がない出来事に意味を見いだして価値判断をしている。不確実性が増大している私たちの時代における企業倫理も、このような意味不明な出来事に対処する必要があるはずだ。このような目論見で、スピノザの『エティカ』を現代風に拡大解釈しようとしているのだけれども、まだまだ先は長く、見通しは立っていない。
科学技術&アートについて考えるとき、個人の活動なのか、組織の活動なのかという問いは、おそらく「組織」に関する考え方の変容、再考が必要になるだろう。産業社会の未来図を考えるとき、最も重要なことは、現代の産業社会では「社会」が不在もしくは機能不全になっているということだ。政治も経済も全て法的に定義された「組織」の活動であって、「組織」には含まれないボランティアなどの個人の活動がなんとか社会を支えている。社会で最も普遍的と思われる「家族」ですら、欧米の離婚訴訟を見ていると、法的に定義された組織でしかないように思われてくる。筆者の未来図は、組織活動を人びととAI機械が協力して行う活動として再定義することから始まる。工場労働者や組織の管理職が、機械的な組織部品となるのではなく、経営者も含めて、「組織」活動における機械的アルゴリズムを、より自然で倫理的な、確率的アルゴリズムにアップデートすることを考えている。行き詰まった社会的「価値」を刷新するためには、意味不明な未踏領域を冒険する勇気が必要だ。技術論の哲学は、社会概念を変革する哲学でもある。
--------------------------------------
『剰余所与論』は意味不明な文章を、「剰余意味」として受け入れることから始めたい。言語の限界としての意味を、データ(所与)の新たなイメージによって乗り越えようとする哲学的な散文です。カール・マルクスが発見した「商品としての労働力」が「剰余価値」を産出する資本主義経済は老化している。老人には耐えがたい荒々しい気候変動の中に、文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試みです。












コメントを残す