山本謙三(やまもと・けんぞう)
 オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。
オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。
異次元緩和の開始から7年半、マイナス金利の導入から5年弱、YCC(イールド・カーブ・コントロール)の実施から4年が過ぎた。銀行はいよいよ苦境に立たされている。
考えてみれば、当たり前だ。預金金利はゼロ%に張り付く。一方、リスク・フリー・レートである国債(10年以下)の市場利回りは、5年近くゼロ近傍にある。負債と資産の金利が同一水準(ゼロ%)であれば、収益をあげるどころか、経費も賄えない。
国債に投資するならば、少しでもプラスの金利のつく超長期債しかない。実際、地域金融機関ではデュレーションの長期化が進む。
しかし、期間が長くなるほど、金利リスクは高まる。もし日本銀行の物価目標(2%)が達成され、国債利回りも2%上昇すれば、20年物国債の市場価格は3割強下がる。超長期債に多額を投資するわけにはいかない(注=本文中の図表は、その該当するところを一度クリックすると「image」画面が出ますので、さらにそれをもう一度クリックすると、大きく鮮明なものを見ることができます)。
◆貸し出し、社債でのリスクテイクも限界
貸し出しや社債への運用はどうか。信用リスクをとり、クレジットスプレッド(貸し出し・社債利回りと国債利回りの差)で収益を稼ごうという算段だ。
しかし、クレジットスプレッドもすでに大幅に縮小した。国債への投資機会を失った資金が、争って貸し出しや社債に向かった結果である。スプレッドは、新型コロナの感染拡大で一時大幅に拡大したが、いまはほぼ元に戻っている。
典型は、日銀の運用利回りだ(注)。日銀が保有する社債の運用利回りは-0.024%だった(2019年度)。
どんなに優良な企業であっても、倒産確率がゼロになることはない。にもかかわらず、マイナスの社債利回り(マイナスのクレジットスプレッド)というのは、日銀の資金供給が市場経済のロジックを押しつぶすほどの大規模に達している証しである。
(注)日銀は、異次元緩和の開始以降、残存3年以内で原則BBB格以上の社債を積極的に買い増してきた。この結果、クレジットスプレッドは大幅に縮小した(今年度は新型コロナへの対応として、買い入れ対象を残存5年以内に拡充)。
市場の歪(ゆが)みは、裁定取引を通じて貸出市場にも波及する。社債と貸し出し、大企業と中堅・中小企業、短期と長期という違いはあっても、ともに企業の信用リスクをやりとりする市場である。全国銀行の預貸金利ざやは、現状0.2%程度にある。
しかし、これには、金利が高めの時期に実行された既存の貸し出しが含まれる。新規の貸出金利だけであれば、過去分を含む残高全体の貸出金利よりも0.1%ほど低い。
貸し出しの満期が到来し更新の都度、貸出残高全体の平均金利は新規の貸出金利に近づいていく。預貸金利ざやは、一層の縮小が避けられない。
(参考1)全国銀行の預貸金利ざやの推移(%、2012年度→19年度)
(出典)全国銀行協会HP「各種統計資料 / 各年度決算」を基に筆者作成
問題は、そうした預貸金利ざやの水準で信用コストを賄えるかどうかである。信用コストとは、貸出先の倒産に伴う損失やこれに備えた引き当てなどの与信関係費用をいう。
銀行の信用コスト率(貸出残高に対する与信関係費用の比率)は、異次元緩和の開始以来、ゼロ近傍にとどまってきた。日銀による巨額の資金供給が企業倒産を抑制してきた結果である(参考2参照)。
しかし、ゼロ近傍の信用コスト率は論理的に永続しない。経済の発展には、企業の新陳代謝が欠かせないからだ。長期的にみれば、信用コスト率は必ず一定のプラスに戻る。
信用コスト率は過去大きく振幅してきたために、歴史的な平均水準を見極めるのが難しい。しかし、これまで貸出市場では、日銀による巨額の資金供給を背景に銀行間の熾烈(しれつ)な貸し出し競争が行われてきた。
そのことを踏まえれば、信用コスト率は、今後相当に高まる可能性があるだろう。0.1~0.2%の預貸金利ざやが将来の信用コストを賄える水準かどうかは、慎重に見る必要がある。
(参考2)大手行、地域銀行の信用コスト、信用コスト率
(出典)日本銀行「2019年度の銀行・信用金庫決算」
◆預金はまだまだ増える
この間、預金は増え続けている。一部に「貸し出しや有価証券への運用が実質的に採算割れならば、預金をとらなければよい」との議論があるが、現実的ではない。
銀行が預金の流入を抑えるには、預金金利をマイナスに引き下げ、預金残高が日々目減りする状態を作る必要がある。しかし、これは単に、預金の流出、すなわち手持ち現金(タンス預金)の増加を引き起こすだけである。
日銀が現金(銀行券)という金利ゼロの決済手段を提供する限り、避けられないことだ。しかし、多額の現金を手持ちするのは盗難リスクを伴い、社会不安を引き起こす。日銀が現金供給に対しなんらかの手当てをしない限り、預金金利のマイナス化は選択肢になりにくい。
◆ハイリスク資産への傾斜
この結果、銀行は、外国証券や不動産、投信などハイリスク資産の運用に傾斜を強めてきた(参考3参照)。大手行は、外国証券の増加が目立つ。一方、地域銀行では、長めの地方債や投信への運用が増加している(新興国を含む国内外の債券や株式などの幅広い資産に投資するマルチアセット型投信を含む)。
そうしなければ収益をあげられないからだが、結果的に抱えるリスク量が増え、銀行システム全体は弱体化している。過去からの蓄積のおかげで、銀行がただちに行き詰まることはないが、自己資本比率の低下傾向は鮮明である。
(参考3)銀行の保有有価証券の商品別利回りと残高(末残)
(出典)日本銀行「2019年度の銀行・信用金庫決算」
ハイリスク資産への運用の傾斜は、実は、日銀が量的緩和の波及経路の一つとして期待してきたものだ。量的緩和により、国債金利をゼロ%、クレジットスプレッドをゼロ近傍に抑え込むことで、株式や不動産、外国証券などへの投資を増やし、資産価格の上昇や円安を誘発する経路である(ポートフォリオ・リバランスの経路)。
実際、銀行はその通りの運用に追い込まれた。にもかかわらず、物価目標2%は7年半が経っても達成されず、銀行システムの弱体化ばかりが進む。「物価目標が人々のインフレ心理を駆り立てる」というロジックを含め、もともとの異次元緩和の理屈に欠陥があったということだろう。
◆新型コロナ対応の貸し出し増加が意味するもの
今年春以降、銀行貸し出しは新型コロナへの対応で大幅に増えた。企業が万一の事態に備えての積み上げを急ぎ、銀行が対応した結果である。
この間も、貸出金利の低下には明確な歯止めがかからない。それでも中小企業向け貸し出しが大幅に増えたのは、制度融資の一環として行われたからだ。
制度融資では、企業は自治体から利子補給を受けられるうえに、信用保証協会から信用保証を受けられる。信用保証があれば、銀行は将来の信用コストをゼロとカウントできる。金融機関がこぞって貸し出しを増やした理由である。
このことは、足元の貸出金利がもはやリスク・リターンに見合わず、信用保証協会による信用コストの肩代わりがあって、はじめて、貸し出しを増やせる状態にあることを示唆している。
日銀も「企業の資金繰りを支援するための貸出制度」をスタートさせた。同制度では、日銀は、利用金融機関に対しマイナス金利の賦課を一部解除するとともに、制度利用残高にプラスの金利(+0.1%)を付与している。
すなわち、表面上のマイナス金利政策の標榜(ひょうぼう)とは裏腹に、真逆の金利を適用している。日銀は率直に語らないが、マイナス金利政策はいまや銀行貸出を阻害する要因になっているということだ。
◆政策パッケージの見直しを
結局、銀行システムは、長期にわたるフラットなイールドカーブ(や逆イールドカーブ)に耐えられない。実際、過去にそうしたイールドカーブが実現したのは、金融引き締め時の短期間に限られている。
そもそも現状は、フラットなイールドカーブ(ゼロ%)を必要とする経済環境でもない。
名目金利は、長期的にみれば「名目成長率見通し(=実質成長率の見通し+物価上昇率の見通し)+リスクプレミアム」で決まる。日本の実質成長率、物価上昇率は、長期でみればプラスの見通しにある。中長期金利がゼロでなければならない理由はない。
プラスの中長期金利をとり戻すには、①金融調節のターゲットを短期金利に一本化する(とりあえず0%に)②国債の買い入れを短期金利ターゲットの実現に必要な最小限の範囲にとどめる③短期金利以外の金利(中長期金利)を市場の自由な裁定に委ねる――が必要だ。
要は、量的緩和、マイナス金利、イールド・カーブ・コントロール、物価目標2%という政策パッケージ全体を見直すことである。
考えてみれば、当たり前だろう。今年度の新規国債発行額(補正後)は、90兆円にのぼる。このような巨額の資金調達をタダで行えるというのは、やはり歪(ゆが)んでいる。

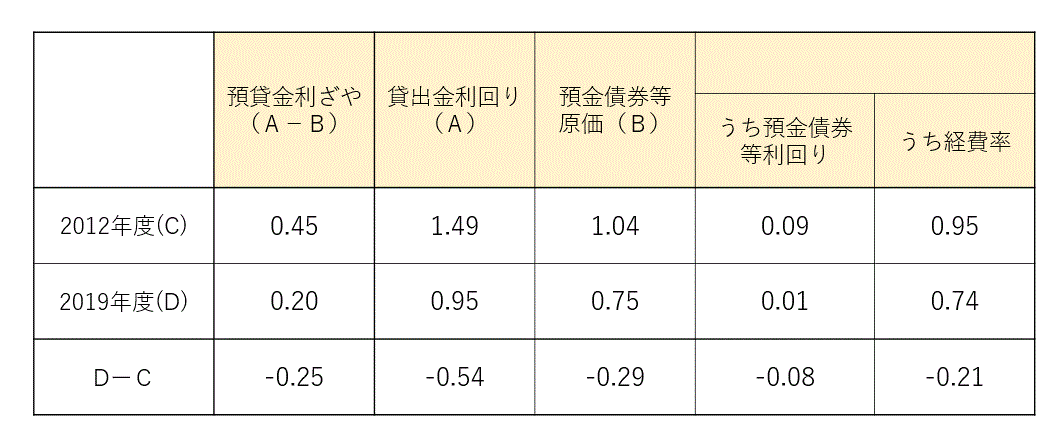
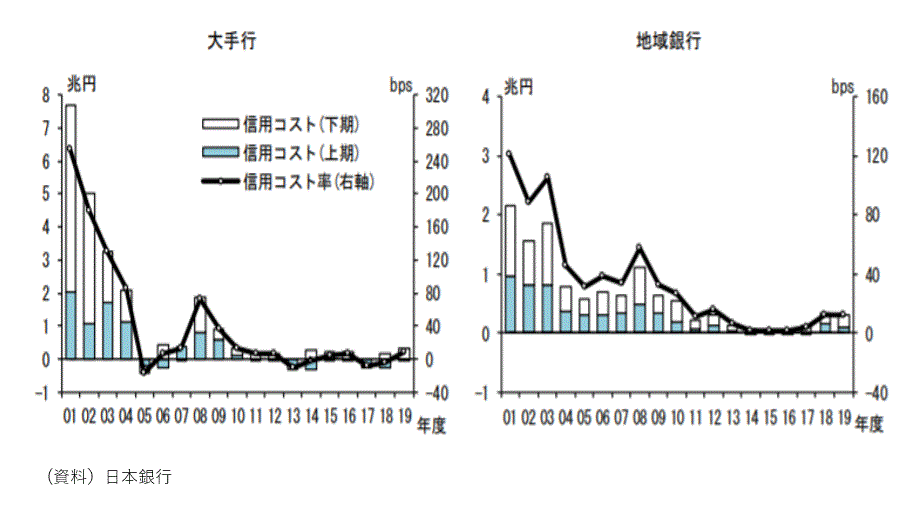
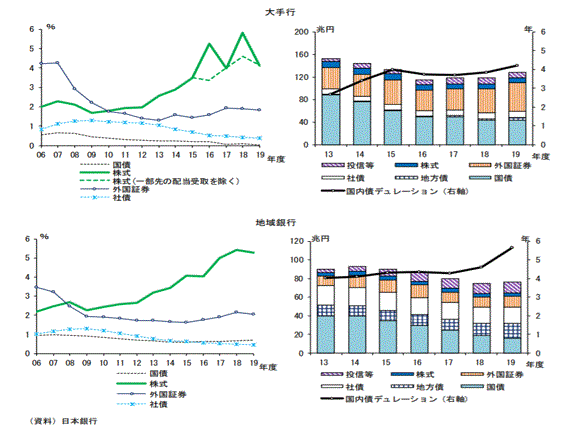










コメントを残す