山本謙三(やまもと・けんぞう)
 オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。
オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。
「人口動態と労働市場」の第3回として、高齢者の労働参加をみてみよう。高齢の就業者は、近年着実に増えてきた。しかし、長寿に見合った増え方だったかといえば、そうではない。働く期間の延びは、寿命の伸びに追いつかない。
生産年齢人口(15~64歳)の減少スピードは、今後一段と加速する。高齢人口の増加スピードも大幅に鈍る。これまで女性、高齢者の就労増で人手不足を回避してきた日本経済だったが、この姿は続かない。
生産年齢人口が減少に転じて25年。いよいよ「本当の人口オーナス」が始まる。
◆実は働かなくなった高齢層
参考1は、65歳以上の男女別労働力人口比率の推移である。労働力人口とは、就業者と完全失業者の合計をいう。大づかみにいえば、実際に働いている人と働こうとしている人の数だ。
1960年代後半は、65歳以上のおよそ3人に1人が労働力人口だった。これが、いまは4人に1人まで低下している。とくに男性の比率低下が著しい。
(参考1)65歳以上の労働力人口比率推移
(出典)総務省統計局「労働力調査結果」を基に筆者作成
比率の低下は、分母となる高齢人口が、長寿化により大幅に増えたことによる。また、第1次産業や自営業など「身体の動く限り働くこと」を慣行としていた産業が、シェアを低下させたことも大きい。代わって増加したのが、いわゆる「サラリーマン」である。定年制のある就労形態の拡大が、高齢男性の労働力人口比率を低下させている。
日本の高齢者は、長寿になったわりに働かなくなった。長生きには、医療費や介護費、生活費がかかる。費用の一部は、財政が負担している。このツケを、国債発行を通じて将来世代に回しているのが、いま日本の姿だ。
◆期待される高齢者の労働参加、それでも自然減を補えない
生産年齢人口が減少を続ける以上、高齢者にはできるだけ長く働いてもらいたいところだ。では、高齢者の就労増で、どれほど日本全体の就業者数を押し上げられるか。前回同様、機械的な試算でイメージを把握してみたい(参考2参照)。
(参考2)2045年の労働力増減推計(万人)
(出典)国立社会保障・人口問題研究所「人口の将来推計(平成29年推計)」、総務省統計局「労働力調査結果」を基に、筆者試算
表の中の「自然減」とは、2020年時点の年齢階層別の労働力人口比率がそのまま維持されると仮定したうえで、次の25年間にどれほど労働力が減るかを試算したものである。参考までに、上段には、1995年時点を想定し20年までの25年間に見込まれた自然減と、実際の変化(実績)を示してある。
1995年から20年までは、全体で約410万人の自然減が生じたと試算される。内訳は、生産年齢人口の約770万人の自然減に対し、高齢人口が約360万人の自然増となる見込みにあった。
ところが、労働力人口全体の実績は199万人の増加となった。約610万人の上振れである。若手・中堅女性の労働参加が約500万人、また高齢者の労働参加が労働力人口を約110万人(男女計)押し上げた。
一方、2020年から45年までの25年間は、自然減は1468万人にのぼる。実に、労働力人口の2割強が失われる計算となる。
過去と今後で自然減にこれほど差が出るのは、生産年齢人口の減少スピードが年率-0.6%から-1.1%に加速することが大きい。また、高齢人口の増加スピードも、年率+2.8%から+0.3%まで鈍化する。長年にわたる少子化の影響が、ついに65歳以上の人口にも及んでくる。
これほどの自然減を、従来のように女性と高齢者の就業増で補うのは、並大抵のことではない。参考2の2つの試算例は、女性と高齢者の労働力人口比率に高めの仮定を置き、どの程度まで自然減を打ち返せるかを試算したものだ。
試算例2は、①女性の労働力人口比率が全年齢層にわたり現在の男性並みまで上昇する、また、②高齢男性の労働力人口比率も65~69歳85%(現在62%)、70歳以上40%(同26%)まで上昇することを仮定した。
いずれも、相当に背伸びをした仮定である。それでも、打ち返せるのは15~64歳女性で約400万人、65歳以上男女で約610万人までだ。自然減と差し引きすれば、約460万人の減少が残る。過去25年のように、自然減を打ち返してなお余りある就業者というのは、望むべくもない。
(注)今後、人口の減少とともに需要の減少も見込まれるため、自然減をすべて埋めなければならないわけではない。しかし、2045年ごろまでは、生産年齢人口が総人口を上回るペースで減少するため、供給力が需要減を超える速さで縮小し、人手不足が加速する。同時に、国の豊かさの指標である「国民1人当たりの成長率」も低下する。国の豊かさを維持するには、労働力人口の増加(社会増)と労働生産性の向上がどうしても必要となる。次回、試算結果を論じたい。
◆カギは定年制の廃止と年金受給開始年齢の引き上げ
それでも、女性、高齢者の就労環境を整え、就業者をできるだけ増やす努力は続けなければならない。では、高齢層の就労を促すには、どうすればよいか。
ヒントは、前掲参考1のグラフにある。男性の労働力人口比率は、低下トレンドの中にも、いくつかの反転・上昇局面があった。1990年代前半、2000年代前半、2010年代前半である。これらの時期は、定年制と年金支給開始年齢の変更に密接に連関している。
第一は、定年の引き上げだ。日本では、55歳定年制が昭和初期から長く続いてきたが、1980年代以降段階的な引き上げが図られ、1990年代に60歳定年が義務化された(94年法改正、98年同施行)。
2000年代に入ると、65歳定年への準備が進められ、2010年代に65歳定年(65歳までの継続雇用)が義務化された(12年法改正、13年施行)。さらに本年4月からは、企業の努力義務として、70歳までの就業確保措置が課されている(20年法改正)。
しかし、少子化・長寿化のスピードに比べれば、定年延長のペースは遅い。現時点で70歳定年の是非を論じても、間に合わない。そもそも米国などでは、定年制は年齢差別として法律で禁じられている。日本がただちに着手すべきは、定年制の廃止だろう。
第二は、年金の支給開始年齢の引き上げである。厚生年金は当初55歳を支給開始年齢としていたが、その後累次の改正により同年齢を引き上げてきた。
1957年度からは16年かけて男性の支給開始年齢が60歳に、87年度からは12年かけて女性の支給開始年齢が60歳に引き上げられた。
その後(老齢)厚生年金の定額部分について、男性は2001年度から12年かけて、女性は06年度から12年かけて、それぞれ65歳に引き上げられた。さらに、(老齢)厚生年金の報酬比例部分について、男性は13年度から12年かけて、女性は18年度から12年かけて65歳に引き上げている最中にある。
年金の支給開始年齢と労働力人口比率(あるいは就業率)には密接な連関がある。年金収入を当てにできる期間が先延ばしされれば、それだけ働く必要が生まれ、就労人口が増える理屈である。
厳しい「ムチ」にみえる。しかし、長生きを享受しながら、財政のツケを将来世代に回すことは、子ども世代への「ムチ」にほかならない。政治は集票を意識して手をこまぬきがちだが、シルバー民主主義の欠陥を克服しなければならない。
それにしても、「人口オーナス」への危機感は乏しい。過去25年間、女性、高齢者の就労増加でプラスの経済成長を維持できたことが「惰性」を生んできたようにみえる。惰性が致命傷を生まないよう、身を引き締め直さなければならない。

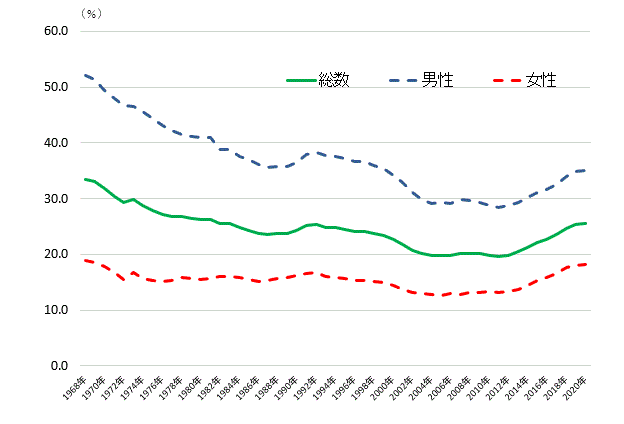
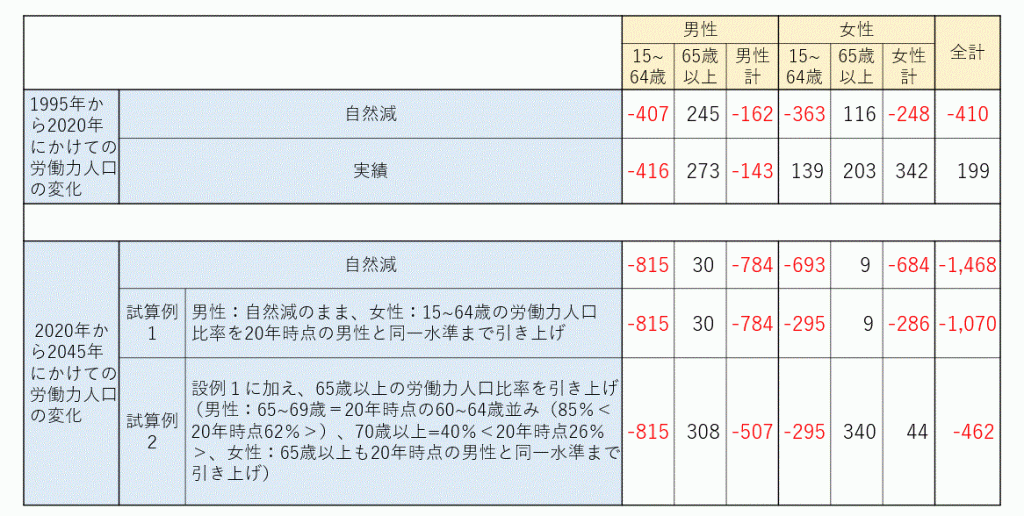










コメントを残す